手のひらに… (2006.2.9〜2.12/寺院時代・illusted by みつまめ様) |
 降り積もる純白の欠片。 降り積もる純白の欠片。重たかった曇天の冬空から舞い落ちる。 冷たい浄化の花びら。 世界を白く染めてゆく無言の絹。
降り出した雪に帰る足を止めて、三蔵は何かに呼ばれたように空を見上げた。 犯した罪と同じ代価の罰。 命を取られてもそれは当然で。 最高僧と呼ばれ、現人神のごとく言われても所詮は世間知らずの若造で。 知っている、自覚もある。 だが、あの無条件の信頼を向けてくる養い子を己の血塗られた道に巻き込むことは出来ない。 贖罪のつもりではないけれど。 あの笑顔が汚れた我が身の救いであるはずで。
雪降り積もり、舞い落ちる。
しんしんと降る雪の中を三蔵が帰ってきた。 「外、雪が降ってたんだろ?」 身体を離して見上げて。 「そんなに冷たかった?」 そっと目の前の三蔵の手を取ったら、三蔵の肩が小さく震えた。 「ほら、俺暖かいよ?」 両手で握って頬に当てた三蔵の手は冷え切って氷のようだった。 「冷たい…でも、こうしてたらすぐ暖かくなるからな」 そう言って笑ったら、三蔵の瞳がちょっとびっくりしたように見開かれた。 「さんぞ…?」 俺の問いかけに何も答えないまま、三蔵はずいぶん長い間、俺を抱きしめていた。 ねえ三蔵、俺の温もりあげるから大丈夫だよ。
柔らかな頬に触れた掌に残る温もり。 雪の何もかもを覆い尽くすような重い白さではなく、汚れたものも綺麗なものも斉しく包み込む陽差しのような白さに、穏やかに解け出してゆく己の矮小な罪の意識。 凍てつく大地を割って芽吹く春の階のように力強く。 この純粋で綺麗な魂に恥じないように、無垢な心を汚さないように、傍らで生きて行けるなら、何を惜しむだろうか。 すやすやと眠る養い子のまだ稚い寝顔に、三蔵は仄かな笑みを浮かべたのだった。
しんしんと降り積もる雪のように、幾重にも重ねて。
|
| close |

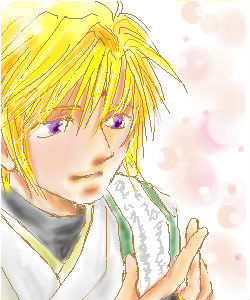 子供の触れた所からじわりと染み込んでくる熱に凍った何かが溶け出す。
子供の触れた所からじわりと染み込んでくる熱に凍った何かが溶け出す。